独身もしくは子供のいない夫婦にも終活する必要はあるのだろうか。
遺される家族や子どもがいないなら誰にも迷惑かけないのではないかな。
そう思っている人も多いのではないでしょうか。
子なし夫婦、おふたりさまの僕もそう思っていました。
しかし、入院や施設入所など身元保証人が必要な場合、自分が困りますし、災害で逃げ遅れたり、孤独死をしたりと、やはり近隣に迷惑をかける可能性はあります。
本記事はおひとりさま、おふたりさまの終活について執筆しました。
最初におひとりさまとおふたりさまの定義を書きました。
次におひとりさま、おふたりさまの終活の特徴についてまとめました。
そして、おひとりさま、おふたりさまが直面しやすい終活の問題を知ることができるでしょう。
是非、最後までお読みください。

ここでは終活における、おひとりさま、おふたりさまの定義を示します。
そもそも終活とは?
そもそも終活とは何なのでしょうか。
終活とは「人生の終わりのための活動」の略称のことをいいます。人生の最期をよりよく迎えるための準備をおこなう活動のことです。
2009年の雑誌連載で「終活」という言葉がはじめて登場し、2012年には流行語大賞にノミネート。2010年前後から終活ブームがはじまり、急激に普及し、一般的に定着しました。
その背景には、核家族化や長寿化などで頼れる家族が少なくなったことが深く関係していました。
おひとりさまとは
「おひとりさま」という言葉ですが、以前は女性の自立した一人行動に「おひとりさま」と呼ぶことが多かったです。
しかし、今は女性に限らず、お店に一人で行く人のことを「おひとりさま」と呼ぶことが一般的になってきました。
飲食店において、来店した一人客に「おひとりさまでしょうか」などという場面はよく見かけますね。
ですが、終活における「おひとりさま」とは同居する人がおらず、一人で生活している人を指します。
独身のほか、パートナーとの死別や離別など理由はさまざまですが、男性・女性など性別での区別はありません。
おふたりさまとは
「おふたりさま」とは一般的に子どものいない夫婦のことを指す言葉で、独身の「おひとりさま」に対する言葉です。
「おふたりさま」とは子どものいない夫婦に限って使われることが多く、飲食店でも二人連れのお客には「二名様」というのが一般的でしょう。
「おふたりさま」という言い方を使うとき、意味は限定的になります。
おひとりさまとおふたりさまの取り巻く環境の変化
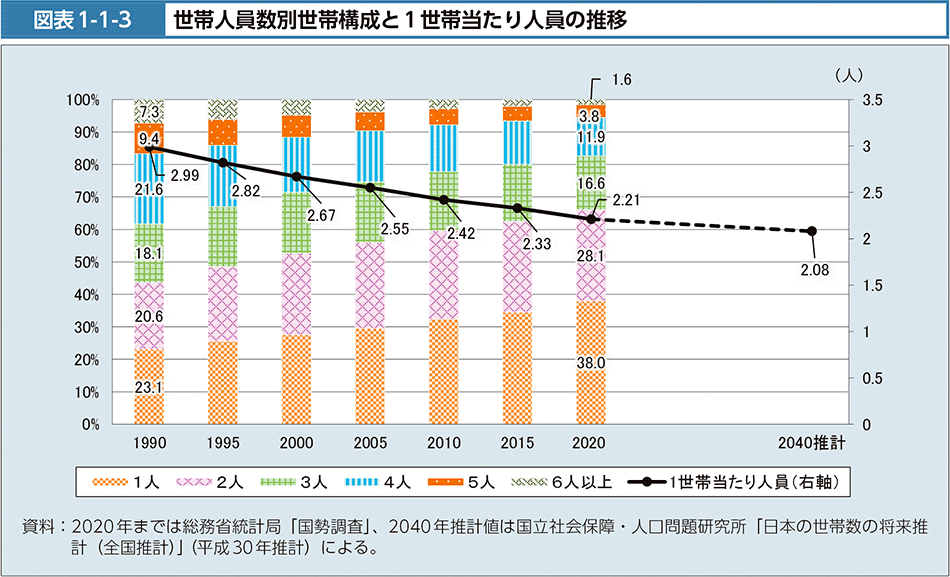
グラフからわかるように、2000年には2人以下の世帯が全世帯の50%を超えました。
そして、2020年には全世帯の約70%が2人以下の世帯になっています。
つまり、10世帯のうち約7世帯が2人以下の世帯ということになります。
それだけ、日本では急速に「おひとりさま」「おふたりさま」が増えてきたということがわかるでしょう。

ここでは、おひとりさま特有の老後問題をご紹介いたします。ご家族のいる方とどのような違いがあるのでしょうか。
病気、けが、災害の場合の対応が遅れる
1つ目は人目につかないために対応が遅れるということです。
病気やけがで発見が遅れると重度の障害が残る恐れもあります。
災害で逃げ遅れた場合も高齢ですと体力も衰えていますので、被害に巻き込まれるリスクも高まるでしょう。
自宅に一人ですと、なかなか人目が届きませんので対応が遅れますが、その備えとして、見守りサービスを利用することをおすすめします。
見守りサービスにもさまざまあり、一例をあげますと、ボタンを押すとスタッフが駆けつけてくれるものやセンサーで定期的に安否確認をしてくれるものなどがあります。
入院や介護が必要になった場合
2つ目は入院や介護が必要になった場合です。
入院や介護施設に入所するには身元保証人が必要となります。
「おひとりさま」の場合、身元保証人がいませんので、入院、施設入所のときに備え、身元保証人を探しておかなければいけません。
一般的には家族・親族になってもらいますが、いない場合は身元保証会社を利用することができるでしょう。
保証会社の形態には、株式会社や一般社団法人、NPO法人などがあり、法人自体が身元保証人となり、介護施設などの連絡窓口になってくれることもあります。
孤 独 死
3つ目は孤独死の問題です。
先述でもありましたように、自宅に一人でいると人目につきにくくなります。
特に入浴中の事故が多く、発見が遅れたために、帰らぬ人になるケースも増えてきています。
「おひとりさま」の不慮の事故の備えとして、いつ万が一があっても、葬儀やお墓のこと、遺品整理など死後のことをご自身の意向どおりに実行してもらうため、死後事務委任契約を締結しておくという方法があります。
死後事務委任契約とは、自分の死後にはさまざまな手続きが必要ですが、これらのことを親族に代わって第三者の業者にやってもらうように契約することです。

ここでは、おふたりさま特有の終活の特徴をみていきます。
夫婦で取り組めるメリット
「おひとりさま」でしたら、全く一人で行わないといけなかった終活ですが、「おふたりさま」の場合は夫婦で協力して進めることができます。
二人で計画を立て、意見を共有し、共通の目標をもつことで一人でする終活よりスムーズで楽しくはかどるでしょう。
どちらかが亡くなったときのデメリット
先述では、夫婦で協力して終活を進めることができると書きましたが、残念ながらどちらかが先に亡くなります。
そうなると「おひとりさま」と同じ状況になります。 ふたりで伴走しながら、いずれはどちらかが「おひとりさま」になる現実を受け止め、いざというときに困らないために、それぞれの終活を進めていくことが大事でしょう。
おふたりさまにおすすめの契約
①遺言書の作成
1つ目のおふたりさまにおすすめは遺言書の作成です。
なぜなら、遺言書を作成しておけば、全財産を配偶者に受け渡せられるように指定することができるからです。
遺言書がなければ、法定相続人に相続されるでしょう。ですので、子どもがいる場合、相続する割合は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
ご自身の意向に沿う遺産相続をしたければ、遺言書を書く必要があります。
②任意後見契約
任意後見契約とは、自分がまだ元気なうちに、将来判断能力が低下した際の財産管理や生活支援を任せる後見人を指定する契約です。
なぜおすすめなのかというと、任意後見契約を締結していれば、後見人に生活や財産の管理を任せることで、不測の事態に備えることができるからです。
この契約を交わすことで、配偶者や第三者に迷惑をかけずに、安心した生活を続けることが可能になります。
具体的なケースとしてはおふたりさまのどちらか一方が判断能力を失ったとき、後見人を事前に決めておくことで配偶者にすべての負担をおわせることを回避することができます。

ここでは、「おひとりさま」と「おふたりさま」の共通の問題点をみていきます。
通常の終活との違い
通常の終活との一番の違いは子どもなどの親族がいないという点でしょう。
ある程度年齢がいくと、できることも限られてきますし、人の手を借りたいときもあるでしょう。
近くに子どもがいれば、すぐに呼べますが、そういう人もいません。 入院や介護施設への入居など身元保証人が必要な場合や死後の手続きなど頼める身内がいないというのが一番の問題です。
「おふたりさま」は「おひとりさま」予備軍でもあります。パートナーも同年代の方が多いでしょうし、少し煩雑な手続きは頼めないケースも少なからずあります。
そんなときに相談できる窓口があると便利ですね。 次にみていきましょう。
身元保証に関する相談窓口の有効利用
おひとりさまで身元保証人を頼める人が見つからない場合、いくつかの相談窓口があります。
相談は無料でできますので、有効に使っていってください。
①自治体
高齢者福祉課などが窓口になる自治体もありますが、多くは地域包括支援センターや社会福祉協議会を紹介され、そこが相談窓口となります。
②地域包括支援センター
地域包括支援センターとは、高齢者の健康面や生活全般に関する相談を受け付けている、地域に密着した総合相談窓口です。 身元保証人に関する公的なサポートを受けられるよう相談に乗っていただけます。
③社会福祉協議会
64歳以下の方は社会福祉協議会が相談窓口となります。 社会福祉協議会は民間組織で地域活動や福祉サービスを行っています。 具体的なサポートとしては、身元保証のほか、就労支援事業などです。
④身元保証会社
身元保証会社とは、保証人を立てることが難しい方に代わり、各種手続きや契約の際に「保証人」としてサポートを行う専門会社です。 入院や施設入居の際の保証人になるだけではなく、死後の事務手続きや、買い物や緊急時の連絡など日常のサポートをしてくれるサービスもあります。
まとめ
近年、日本では「おひとりさま」「おふたりさま」と呼ばれる単身者や子どものいない夫婦の増加に伴い、終活(人生の終わりに備える活動)の重要性が高まっています。
終活とは、死後の手続きや医療・介護、財産管理などについて事前に準備し、人生の最期をより良く迎えるための活動を指します。
「おひとりさま」とは、配偶者と死別や離別をしたり、独身で同居人のいない人を指し、「おふたりさま」は子どものいない夫婦を意味します。
2000年には2人以下の世帯が全体の50%を超え、2020年には約70%にまで増加しており、終活が必要な層が急速に広がっています。
おひとりさま特有の課題には、病気や災害時の発見遅れ、入院・介護時に必要な身元保証人の不在、孤独死のリスクなどがあり、それらに備えるためには見守りサービスや身元保証会社、死後事務委任契約の利用が有効です。
おふたりさまの終活には、夫婦で協力して計画を立てられるという利点があります。意見を共有しながら進めることで、ひとりで行うよりも円滑で前向きに取り組める点が特徴です。
しかし、いずれどちらかが先に亡くなり「おひとりさま」となる現実もあり、それぞれが個別に終活を進めておくことも重要です。
おすすめの契約としては、まず遺言書の作成があります。 遺言書があれば、自分の意思で財産を配偶者に確実に相続させることが可能であり、子どもがいる場合の法定相続分による分割を避けることができます。
次に任意後見契約も有効です。これは、将来判断能力が低下した際に備え、信頼できる後見人に財産管理や生活支援を任せる契約であり、配偶者や周囲の負担を軽減し、安心した老後を送るために役立ちます。
おひとりさま・おふたりさまが直面しやすい共通の終活の課題は、頼れる親族がいないという点です。 入院や死後の手続きなどを自力で行うことが難しくなる場合に備え、地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体などの公的相談窓口や、身元保証会社の活用が大切です。
以上、「おひとりさま」と「おふたりさま」の終活について執筆いたしました。
少しでも、皆さまのお役に立っていれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
当ブログへのご連絡は、以下のフォームからご連絡ください。


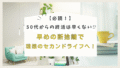
コメント