親もいい歳になってきて、考えたくはないけど、万が一のときのことがふと頭をよぎることが多くなってきた方もいるのではないでしょうか。
親が旅立っても、悲嘆に暮れているひまはありません。葬儀のこと、親類への連絡、身辺整理、銀行口座のこと、などなど、やることは山積みです。
しかし、突然いざというときがやってきたら、何から手を付けたらいいのかわからないですよね。
私もここ数年、親が入退院を繰り返し、親の終活について考えるようになりました。
本記事では終活の資格を取った筆者が、初心者向けに終活の全体像を紹介します。
また、子世代からみる終活と親世代からみる終活の違いをみていきます。 そして、具体的に何から準備すべきかを書きましたので、ぜひ最後まで読んでいただき、今後の参考にしていただければ幸いです。

そもそも終活とは何のことなのでしょうか。
終活とは「人生の終わりのための活動」の略称のことをいいます。人生の最期をよりよく迎えるための準備をおこなう活動のことです。
2009年の雑誌連載で「終活」という言葉がはじめて登場し、2012年には流行語大賞にノミネート。2010年前後から終活ブームがはじまり、急激に普及し、一般的に定着しました。
その背景には、核家族化や長寿化などで頼れる家族が少なくなったことが深く関係していたのでした。
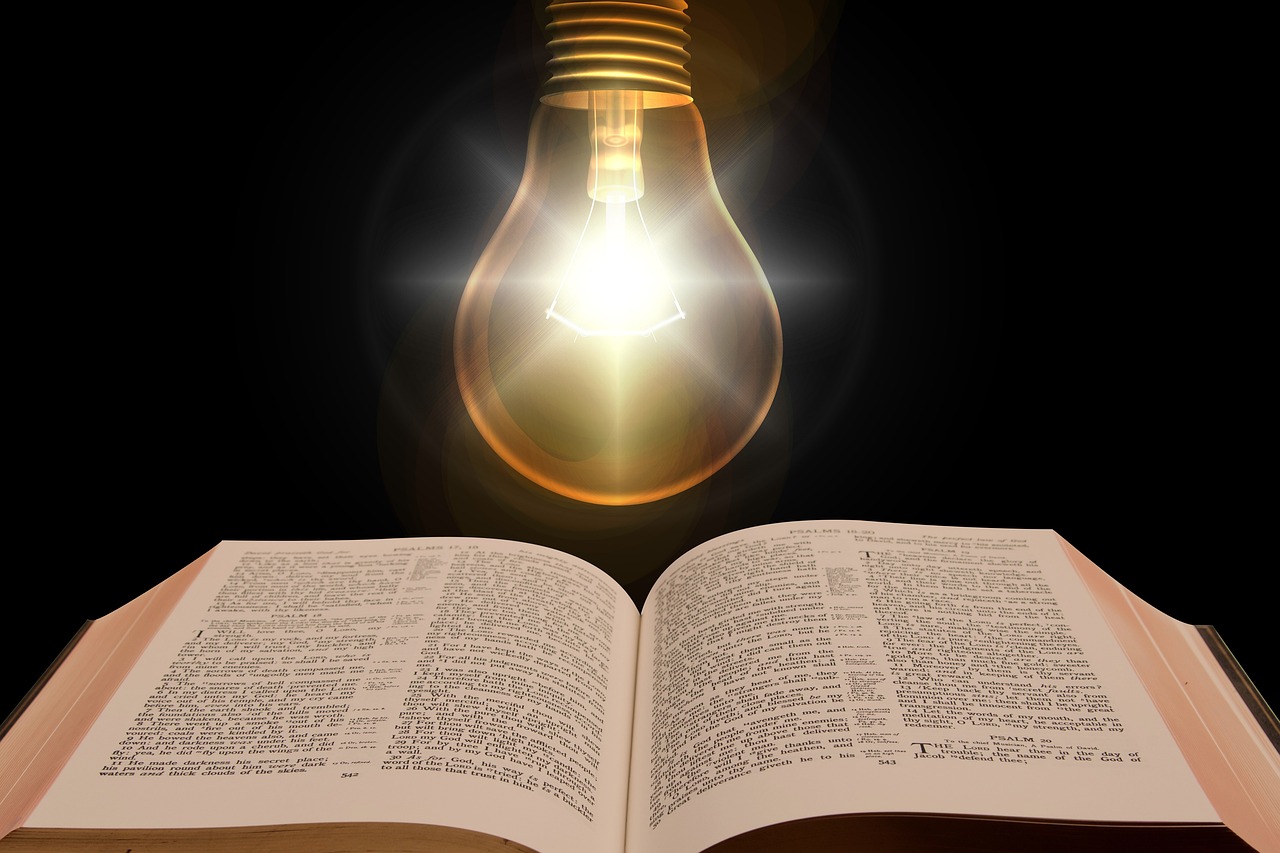
ここでは、主に終活をすることのメリットを3つご紹介いたします。
老後の不安を解消し、充実した生活を送れる
1つ目は老後の不安を解消し、充実した生活を送れるという点です。
なぜなら、エンディングまでの道筋が明確になるからです。 たとえば、定年退職を迎えた方なら、会社に行くこともなくなるでしょう。年金暮らしがはじまり、生活は一変します。
これまでのサラリーマン生活とは違い、実入りも限られてくるので、不安な方も多いはず。
そこで、終活をすることで、ご自身のエンディングまで何をしたいのか、どう過ごしていきたいのか、そうするにはどれぐらいのお金が必要なのかが明確になってきます。 不安は解消され、充実したセカンドライフを送ることができるでしょう。
遺された家族に迷惑をかけなくて済む
2つ目は、遺された家族に迷惑をかけなくて済むという点です。
「死人に口なし」といいますが、亡くなってからでは、遺された家族は本人の意向を聞くことはできません。
しかし、終活をしていれば、遺された家族もスムーズにすべきことを進めることができます。 エンディングノートにご自身の意向、必要な情報を記載しておきましょう。
たとえば、「葬儀はどうしてほしいのか」、「どの範囲まで知らせてほしいのか」や、本籍やマイナンバーカードなどの個人情報を記載しておきます。 終活をすることで、万が一のときの家族の負担を軽くすることができますね。
遺産相続のトラブルを防止できる
3つ目は、遺産相続のトラブルを防止できるという点です。
あらかじめ遺言書を作成しておけば、誰にどの財産を相続させたいのかを明確に伝えることができ、相続人同士の意見の食い違いや争いを未然に防ぐことができるでしょう。
特に、子どもが複数いる場合や、再婚などで家族構成が複雑になっている場合には、遺産分割をめぐるトラブルが起きやすくなります。
そういった場合でも、終活を通じて自分の意志をしっかりと伝えておくことで、遺された家族のもめごとを回避できるでしょう。

離れた実家に住む両親が心配。もの持ちのいい両親なので、なかなか身辺整理も進まなさそう。 とはいえ、終活というデリケートな話題をどう切り出していいのかわからない。 悶々と過ごす子世代のみなさんの終活の悩みを解決していきます。
なぜ子世代の終活が必要なのか
そもそも、なぜ私たち子世代の終活が必要なのかについて2点述べていきます。
親のため
私たちを生み育ててくれた親です。いつまでたっても親は親、子は子。
老後やエンディングは感謝の念を持ち、親の希望を尊重したいというのは、当然の気持ちではないでしょうか。
人生の最期、親をたたえる最大限の行為として、終活に関わることが必要です。
自身のため
親の老後生活で介護が必要になった時、どのような施設にどの範囲でお願いするのか事前に予備知識を入れておけば、実際にそうなったとき、あわてずに対応できますね。
また、親が旅立ったとき、葬儀のこと、相続手続き全般、もろもろすべきことはあります。悲しみのなか、さまざまな手続きをするのはストレスですが、さらに親の意向や必要な情報がなければ、遺された家族は疲れきってしまいます。
追い打ちをかけて、遺産相続でもめることになれば、最悪の事態になりかねません。 自身も家族も守るためにも親の終活に関わることは大事です。
親とのコミュニケーション
終活について親世代の大半が子どもと相談したいと思っています。
にもかかわらず、話題が話題だけになかなか話し合う機会を作るのがむずかしいです。
しかし、親子間でじっくり話し合えれば、お互いに安心感が生まれます。 親の自分史を作るのに、あなたが生まれたときの親の気持ち、あなたが子どもの頃につれていってもらった家族旅行の思い出など、懐かしい話に花が咲くことでしょう。
そして、両者納得のいく深い話ができれば、親子の絆がさらに深まること間違いなし。
話し合うタイミング
それでは、終活というデリケートな話題をどう切り出せばいいのでしょうか。
1つには共通の知人や芸能人など身近な人たちの事例をあげることです。 あの人も終活をしているのかとか、終活をするのは一般的なことなのだと思ってもらえれば、前向きに考えてもらえるきっかけになるはずです。
もう一つは、自分自身が終活をするということです。 自分自身が終活をすることで何をすればいいかわかりますし、自分で終活を進めるのは億劫だと思っている親とも伴走して進めることができます。 また、終活をする自分自身の姿を見せることで親もやってみようという気になるでしょう。

ここでは親世代の終活について、親はどう思っているのか、親にどうしてあげたらいいのかを見ていきます。
子に迷惑をかけたくない
親世代が終活をしようと思う一番の理由は子どもに迷惑をかけたくないということです。
自分が実際に自分の親の臨終のときに苦労した経験があるからです。 必要な書類、必要な情報がどこにあるのかさっぱりわからない、もっと整理されていたらこんなに疲弊せずにすんだのにと思ったに違いありません。
子どもには同じ苦労をさせたくない、というのは親心として当然ですね。 でも、実際に親子間でちゃんと話をできている家族は少ないということです。 親も子も想いがあるのなら、お互いのために一歩踏みだすことが大事ですね。
専門家によるアドバイス
終活に関して、基本的には私たち子世代は親世代と伴走をしますが、相続や遺言書など、法律に関することは弁護士や行政書士に依頼するのがベストです。 書類の不備などで法的効力を失うとせっかくの親の意向が台無しになってしまうからです。

ここからは、終活を進めていくうえですべきことを6つ、順番に見ていきたいと思います。
1.エンディングノートの作成
まず取り組むのはエンディングノートの作成です。
エンディングノートとは基本情報や身の回りのことなど、終活に関する項目を記載しておくノートです。 書店やネットショッピングで購入することができ、さまざまな種類のものがあります。
お好みの一冊を見つけて、作成していきましょう。 以下、エンディングノートの記載項目の一例です。
- 自身に関する基本情報(自身の名前、生年月日、本籍や遺言書の有無等)
- 財産・資産 ・年金・保険(加入年金の種類、加入保険の種類、受取人、連絡先など)
- 医療・介護の希望
- 葬儀
- 埋葬の希望
- 関係連絡先
- 公共料金の契約内容
エンディングノートに記載する内容はとても多く、なかには気持ちの整理が必要な事柄もあります。
ですので、一度に全ての項目を完成させようとせず、書きやすいところから少しずつ記入していくのがおすすめです。
また、エンディングノートをせっかく書いても、その存在を誰にも知らせていないと、いざというとき身近な人が困ってしまいます。
エンディングノートがあることを信頼できる人だけに伝えておき、普段は大切なものを保管する場所にしまっておきましょう。
2.身辺整理をする
体力のあるうちに、身の回りの整理をしていきましょう。
家具・家電などの大きな物の処分は事前に予約が必要であったり、人手が必要だったりしますので、ある程度、予定を立てて進めるのがおすすめです。 また、物もちのいい親世代はなかなか物を捨てられない人もいます。すっきり整理するには思い切って断捨離をしていく必要があります。
1年以上使っていないものは捨てるなど、一定のルールを決めて、部屋を整理していきましょう。 買い手のありそうな物はメルカリなどフリマアプリを使って売れば、捨てるのがもったいない親世代も納得してくれるのではないでしょうか。
3.財産の整理をする
預貯金、口座、有価証券、不動産、その他の資産、借りているお金、貸しているお金などの財産・資産の一覧を作りましょう。
最近はネットだけの金融口座も増えていますので、家族がその情報を知らなければ、知らずに見過ごされる可能性もあります。 デジタル遺産のパスワードなども限られた人に残せるよう保管しましょう。
また、口座やクレジットカードも同時に整理するのをおすすめします。使っていない口座やクレジットカードは解約し、なるべくまとめておくとよいでしょう。
死後整理でたくさんの口座が残っていると遺された家族に多くの手間がかかります。 家族に負担をかけないためにも財産の整理が必要です。
4.老後の介護・医療の意向をまとめる
元気なうちはいいですが、大きな病気や認知症など介護が必要になり、自分の意思表示が難しい状況になることもあります。
お薬手帳など普段飲んでいる薬の情報やかかりつけの医者の情報なども整理しておきましょう。
また、病気の告知の希望、延命治療など終末期の意向も記しておくと、家族は動揺せずに判断できます。
さらに介護が必要な状態になったとき、どこで介護を受けたいのか、家がいいのか、介護施設がいいのかや誰に受けたいのか、家族なのか、ヘルパーさんなのか、決めておくと本人も家族も、そうなった後もすっきり生活を送ることができます。
生前でも意思表示ができない状態になることもありますので、介護・医療の意向をまとめておくことも不可欠です。
5.葬儀などの意向をまとめる
生前に葬儀の話なんて縁起でもない、という人もいるかもしれませんが、何もきまっていなければ、遺された家族にとって大きな負担となります。
《葬儀に関して記しておく意向の具体例》
- 宗派の確認
- 家族葬か一般葬か
- どこの葬儀社で行いたいのか
- 遺影の希望
- 誰を呼びたいか、どの範囲まで連絡するのか
- 喪主の希望 など
ほかに、お墓に関しても考えをまとめておくと安心です。 たとえば、お墓の有無です。 先祖代々のお墓があるのか、新たに購入するのか。 さらにお墓を持たない選択肢もあります。後継ぎがいない場合は、納骨堂などへの永代供養も一般的になってきています。
6.相続の整理をする
遺産相続の準備について3点にまとめましたので解説していきます。
・財産・資産を一覧にまとめる
ほとんどの財産が相続の対象となります。それはプラスの財産だけではなく、ローンなどマイナスの財産も含みます。財産目録を作ると家族にも一目瞭然となり、わかりやすいです。
・戸籍謄本を準備しておく
法定相続人を明確にするため、相続には自身が生まれてから亡くなるまでの「戸籍謄本」が必要です。事前に準備しておくことで、家族もスムーズに相続の手続きを行うことができます。
・遺言書を作成する
法律で規定された方式に則った遺言書は法的効力をもちます。よって、自分の意志で相続人を決めることができますし、遺された家族間のトラブルを防止することにつながります。 他にも相続税対策など、家族の負担を軽くするのに配慮した対策といえます。

本記事では、親の終活に向き合う子世代に向けて、終活の全体像と具体的な準備について解説しました。
終活とは人生の終わりに向けた準備活動であり、老後の不安を軽減し、遺された家族に迷惑をかけず、相続トラブルの防止にもつながります。
親子で終活について話し合うことは、親の希望を尊重し、家族の絆を深める大切な機会となるでしょう。
終活のステップとしては、エンディングノートの作成、身辺や財産の整理、医療・介護・葬儀の意向整理、相続の準備などがあり、早めに少しずつ取り組むことが重要です。
特に財産や相続のことは、専門家の力を借りて正しく進めることが安心につながります。 終活は親のためだけでなく、自分自身と家族の未来を守る行動となりえるでしょう。
この記事が、終活への第一歩を踏みだすきっかけになれば幸いです。
【当ブログへのご連絡は、以下のフォームからご連絡ください】


コメント