「定年退職まではもう少し時間があるし、終活のことはまだ考えなくていいかな」。そうお考えの50代の方も多々いらっしゃるのではないでしょうか。
私も50代が射程圏内に入ってきましたが、まだ現役バリバリ世代だし、終活は早いと思っていました。
しかし、最近実家の親が「あれを処分したいから運んでほしい」「これは使えそうだから持って帰らないか」と言います。
やはり年齢がいってからでは、両親2人ではなかなかはかどらないのが現状。
そこで今回は「50代での終活、断捨離」について執筆いたしました。
断捨離とは不要な物を断ち、捨て、執着から離れることを意味し、心の整理にもつながります。
特に50代から始めることで、体力のあるうちに無理なく進められ、突然の万が一への備えにもなります。
また、セカンドライフを前向きに描けるようになります。
基本ステップは、①計画を立てる、②部屋ごとに区分けする、③「いる・いらない・保留」の3分類で仕分けすること。
注意点としては、思い出の品や高価な物、緊急時に必要な物は慎重に扱い、家族の物を捨てる際は必ず確認を取ることが大切です。
なぜ断捨離をしなければいけないのか。また、どうして50代から断捨離をはじめないといけないのかがわかります。
さらに断捨離の進め方や注意点を解説いたしました。
他にも衣類や食器など種類別の整理術もご紹介。
すっきりとゆったりと老後生活を送りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

ここでは、なぜ断捨離をする必要性があるのかを解説いたします。
断捨離とは
断捨離とは、不要な物を「断ち」「捨て」、物への執着から「離れる」ことにより、「もったいない」という固定観念に凝り固まってしまった心を解き放とうとする考えで、もとはヨガの思想からきたものです。
「断捨離」という言葉は、やましたひでこさんが2009年に出版した『新・片付け術 断捨離』のヒットにより一般的に知られるようになりました。
なぜ断捨離をしなければいけないのか
①家族の負担を軽減させるため
1つ目は家族の負担を軽減させるためです。
ご自身が亡くなったとき、家族は葬儀やさまざまな手続きに追われます。 さらに追い打ちをかけて家の中が物でいっぱいだと遺品整理のことを考えるだけで家族は疲れきってしまいます。
労力や時間、費用などがかかることになり、家族に迷惑をかけます。
ですが、断捨離をしていれば、家族が遺品整理をする負担を減らすことができるでしょう。
②健康のリスクを軽減するため
2つ目は健康のリスクを軽減するためです。
家の中に物が多いと、蹴とばしたり、つまずいたりしますし、転んだときに物にあたってケガをします。
掃除もしにくくなり、衛生的にもよくないでしょう。
病気のリスクにもなります。
断捨離をしていれば、部屋はすっきりし、安全で清潔な環境を保つことができます。
③老後を控え、心も気分も整理できる
3つ目は心も気分も整理できることです。
部屋がすっきりすることで、気分もすっきり晴ればれし、前向きになります。
また、思い出の品を整理しながら、昔の思い出を振り返り、記憶の整理ができます。
それがまた、老後生活のスタートの準備にもなるでしょう。
以上、3点を読んでいただき、断捨離の必要性を感じていただけたのではないでしょうか。

では、なぜ50代から断捨離をはじめないといけないのか、詳しくみていきましょう。
体力のあるうちにやっておく
冒頭でも述べましたように、最近実家に荷物を移動させる手伝いに行くことが多くなりました。
私の父は現役世代のときは家の模様替えなど何でも一人で黙々とする人でした。
ですが、70代になり、さすがに体力的な衰えは目に見えてわかるようになりました。
頭で思ったように以前のようには体が動かないのもストレスでしょうし、何度も息子を呼び出すのも気を遣うでしょう。
年齢がいってから、そういうストレスを少なくするためにも、50代からはじめておくことをおすすめします。
いつ万が一が起こるかわからないので早めに準備する
前述に「家族の負担を軽減するため」とあるように、断捨離をせずに亡くなった場合、遺された家族は遺品整理をする負担が増えます。
いつか終活をはじめようと思っていても、突然万が一がやってくるかもしれません。
そうなると断捨離をしていないのと同じです。
死亡リスクの少ない50代からがおすすめです。
セカンドライフがイメージできる
現役世代をやりきり、定年退職するとセカンドライフが待っています。
50代で断捨離をしておくと、心も脳もすっきりと整理され、クリアにセカンドライフをイメージすることができます。
老後生活を謳歌するため50代の断捨離をおすすめします。
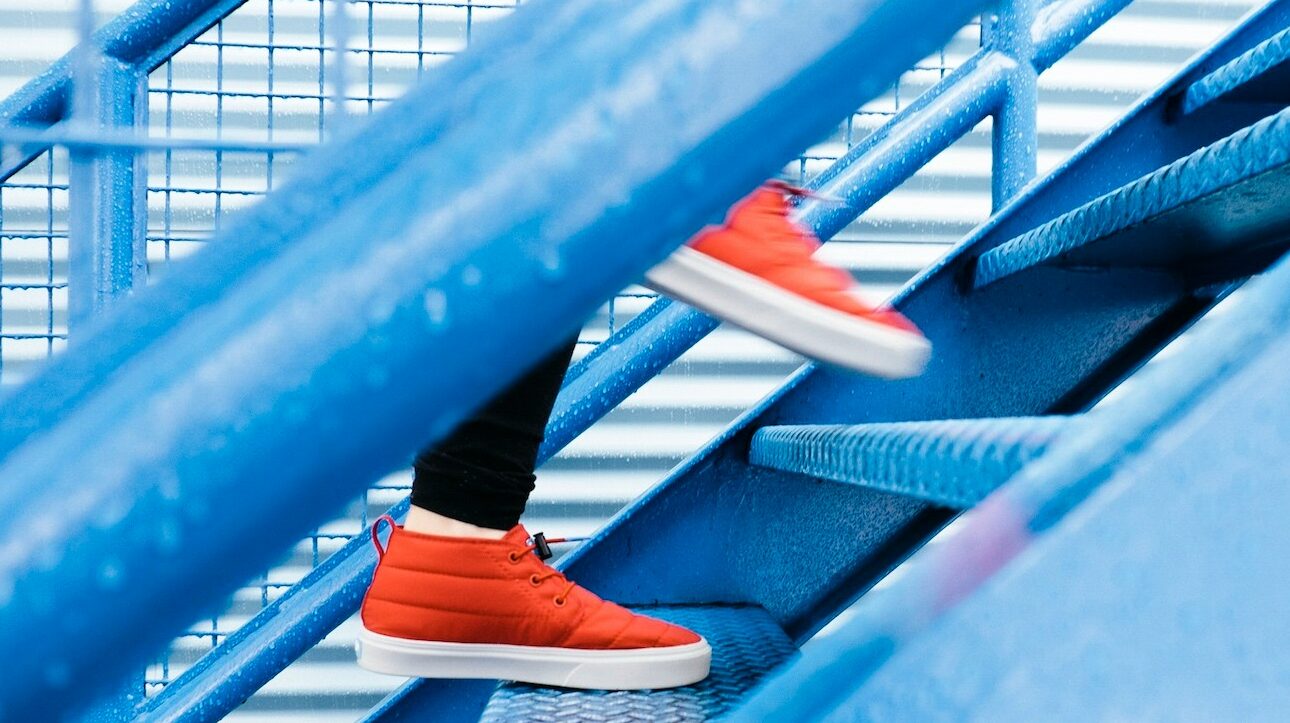
計画を立てる
まずは計画を立てます。いつまでに完了したいのか、どこの部分をいつまでに仕上げるのかなど具体的に決めていきます。
ただし、ここで注意してほしいことは無理なく余裕を持ったスケジューリングをするということです。
計画と進捗が大幅にずれれば、挫折する原因になるからです。
区分けして整理する
次に部屋ごとに区分けをします。家の中を一気に整理するのは大変ですが、リビング、ダイニング、キッチンなどカテゴリーごとに分ければ、より具体的に進捗状況を把握でき、片付いている実感がわきます。
3種類の仕分けをする
いる物といらない物と保留の3つに分ける
①いる物
・頻繁に使う物ー言わずもがなです
・頻度は少ないが必ず使う物ー冷静に判断して残します
・たいせつな思い出の物ー引き継げるものは家族に引き継ぎます
②いらない物
・売却するー使えるけど不要な物はフリマアプリで売ると多少のお金にはなりますし、ゴミにならず、環境への配慮にもなります。
・寄付・譲渡するー寄付を受け付けている支援団体に寄付することは社会貢献につながります。また、家族や友人、知人への譲渡もリサイクルになり、環境保護につながります。
・処分するーいらない物の処理の方法は詳しく後述いたします。
③保留
少しスペースをとることになりますが、いるかいらないか迷った物は一旦保留ボックスに入れておきます。
保留ボックスを作ることで、3つ目の選択肢ができ、結局は時短につながります。
また、一定期間あけて、改めて判断するので、後悔することが少なくなります。

ここまで断捨離をおすすめしてきましたが、ここでは注意すべき点について解説していきます。
むやみやたらに捨てすぎない
断捨離と言っても、当然のことながら、なんでもかんでも捨てていいというわけではありません。
前述した3種類の仕分けをうまく使って、必要な物だけ残します。
勢いに任せて後悔しないよう冷静な判断をしましょう。
特に注意すべきなのが思い出の品、高価な物、緊急時に必要な物です。
1つずつみていきましょう。
■思い出の品
1つ目は写真、手紙、色紙など、金額では計れない思い出の詰まったもの。 2度と手に入らない物なので慎重な判断をしましょう。
■高価な物
2つ目は貴金属やブランド品など高価な物です。 処分する前に買い取ってもらえるか業者さんに査定に出すのもいいでしょう。
■緊急時に必要な物
3つ目は喪服や防災グッズなど緊急時に必要なものです。 使う頻度は少ないですが、いざというときにないと困るアイテムです。
家族の物を捨てるときは、相手に確認する
断捨離する際、家族や同居人の物を無断で捨てるのはNG行為です。
1つ屋根の下に住む人との人間関係の悪化は致命的と言えるでしょう。
共用スペースにある物は必ず相手に許可を取ってから捨てるようにしましょう。
基本的に断捨離するのは自分の物だけです。
トラブルにならないために家族や同居人とルール作りをするのもいいでしょう。

リビングをきれいに保つコツ
テーブルに置くものは最低限にする
新聞や郵便物、小物などでテーブルはすぐに散らかってしまいます。
郵便物入れ、小物入れなど、それほど場所を取らない収納ボックスを置き、他の物は極力置かないようにしましょう。
書類を書いたり、ちょっとした作業をしたりするのにテーブルに十分なスペースがあるとスムーズにはかどりますね。
収納スペースに余裕をもたせる
収納スペースに物をパンパンに詰め込んでしまうと、取り出しにくかったり、他の物に埋もれてなかなか見つからなかったりします。
収納スペースに2~3割余裕をもたせておくことで、出したものが元通りに入らなくても空いたスペースがありますし、物の入れ替えもしやすくなります。
衣類・着物の収納テクニック
衣類の収納テクニック
衣類の収納の基本は3種類です。
①立てて収納
立てて収納すると、どこに何があるか一目瞭然です。
寝かせて積み重ねていくと、下のほうには何があるかわかりませんし、着る頻度も減ってきます。
結局、着るものが偏ってしまい、上手に着まわすことができません。
②吊るして収納
忙しくて洗濯物をたたむ時間がないという方はハンガーにかけて収納するのをおすすめします。
服がシワになりにくいのがポイントです。
③箱に入れて収納
たんすに入れると衣服がぐちゃぐちゃになるという方には箱に入れて収納するのをおすすめします。
種類によって箱を分ければ、すっきり整理されて、結局は時短にもつながります。
着物の収納テクニック
着物は桐たんすで保管するのが一般的です。桐たんすは通気性を良くしたり、湿気や虫の侵入を防いだりする働きがあり、着物の保管には最適です。
しかしながら、桐たんすをお持ちでない方も多くいらっしゃると思います。 そこでクローゼットにしまうときの方法を解説いたします。
①プラスチックケースでの収納
湿気から着物を守るため、すの子や除湿シートを敷きます。収納ケースのサイズは着物を三つ折りにしたときに収まるぐらいのサイズが適しています。
②不織布の衣装ケース(着物用)での収納
不織布は通気性に優れているので、着物の保管に向いています。
ケース自体がやわらかいので、重ねて収納することができません。着物を何着もお持ちの方は場所をとるでしょう。
③着物用ハンガーでの収納
着物用のハンガーがあり、たたんで着物をかけておけます。
ハンガーですとシワになりにくく、通気性もいい状態で収納できますね。
キッチン・食器の断捨離実践例
キッチンまわりは毎日使うところなので、なるべくすっきりさせておきたいところです。
しかし、使用頻度が高いからこそ調理スペースに小物が散在しがちです。
ここでは、キッチンまわりの断捨離を解説いたします。
キッチンの断捨離実践例
キッチンには少量ずつしか使わない調味料がだんだんたまってくる傾向があります。
賞味期限が切れていることもよくあることなので、年に一度は点検し、整理しましょう。
また、キッチンの収納棚にはいつか使うだろうと思って残しているコンビニでもらった割りばしやお手拭きがいつの間にかたまってきます。
実際使うことはまれですので、ストックは1、2本にしましょう。
処分するものは捨てると資源の無駄になるので、取り分ける箸に使ったり、先にティッシュをつけて油とりに使ったり、シンクの掃除道具として使ったりするといいでしょう。
家で割り箸を使わないのなら、コンビニのお会計のときにもらわないのがSDGsにもつながりますね。
食器の断捨離実践例
食器の断捨離も古い物から順番に処分していきますが、上等で使用頻度の少ない来客用の食器は捨ててしまうのはもったいないですね。
順番がきたら、日常用にまわしていきましょう。
柄もきれいで高価な器に日常の中に少し特別感もあり、食事のテンションもあがることでしょう。

思い出・手紙・写真など感情が残る物への向き合い方
想いのこもった手紙、思い出の詰まった写真などは捨てにくいものです。その対処法をみていきましょう。
手紙や写真は劣化しますし、子どもの頃からの累積したアルバムはかさばります。劣化も防ぎ、コンパクトにするにはデータ化するのがおすすめです。
データ化したあとは、手紙や写真は家庭の可燃ゴミとして捨ててかまいません。
しかし、想いがあったり、個人情報があったりで、どうしても可燃ゴミとして捨てにくいという方は、神社やお寺の「お焚き上げ」を利用したり、ヤマト運輸や日本郵便などが提供している「機密文書廃棄サービス」を利用するとよいでしょう。
フリマアプリ・買取業者・自治体回収の活用方法
ここでは仕分けした不用品の処分方法をみていきたいと思います。
フリマアプリで売却する
十分使えそうな不用品はフリマアプリで売却します。メルカリやヤフーオークション、ラクマなど、簡単に出品することができます。リサイクルにもなり、多少の利益も出ます。
買取業者に依頼する
リサイクルショップに持ち込んだり、大量であれば、出張買取をしてくれる業者もあります。
自治体に回収依頼をする
一般ゴミでは出せないもの、事前に回収シールを購入して、不用品に貼って、ゴミに出すものなど、各自治体によって決まりがありますので、それに従って出すようにしましょう。

![]() 遺品整理110番は日本全国において24時間365日、遺品整理に関するサービスを幅広く提供しており、累計問い合わせ件数は500万件以上にのぼります。
遺品整理110番は日本全国において24時間365日、遺品整理に関するサービスを幅広く提供しており、累計問い合わせ件数は500万件以上にのぼります。
ライフリセットは全国対応、最短10分、累計3,000件の信頼実績です。
満足度99%に挑戦中。
バイセルは独自の販売販路があります。ですので、高価買取が可能です。
![]()

今回は「50代での終活、断捨離」について書いてきました。
断捨離とは不要な物を断ち、捨て、執着から離れることを意味し、心の整理にもつながります。
特に50代から始めることで、体力のあるうちに無理なく進められ、突然の万が一への備えにもなります。
また、セカンドライフを前向きに描けるようになるでしょう。
基本ステップは、①計画を立てる、②部屋ごとに区分けする、③「いる・いらない・保留」の3分類で仕分けすること。
注意点としては、思い出の品や高価な物、緊急時に必要な物は慎重に扱い、家族の物を捨てる際は必ず確認を取ることが大切です。
暮らしの中の身辺整理では、リビングや衣類、キッチンなど日常空間をすっきり保つ工夫が大切でした。
リビングはテーブル上の物を最小限にし、収納には余裕をもたせることで快適さが向上します。
衣類収納は「立てる・吊るす・箱に入れる」の三種類が効果的で、着物は桐たんすが理想ですが、プラスチックケースや不織布ケース、着物用ハンガーでも保管可能です。
キッチンは使わない調味料や割りばしの細かいものの整理がポイントで、使い切る工夫も大切でした。
来客用の食器は日常使いにまわすことで無駄を防げます。
捨てにくい思い出の品はデータ化やお焚き上げ、機密文書処理サービスの活用が有効です。
不用品はフリマアプリ、買取業者、自治体回収などで適切に処分しましょう。
整理整頓は心の整理にもつながります。
以上、50代の終活、断捨離についてでした。
少しでも皆さまのお役に立っていれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
当ブログへのご連絡は、以下のフォームからご連絡ください。

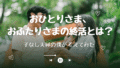
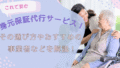
コメント