終活をはじめようとお考えのおひとりさま、おふたりさまにとって、入院時や死後のことなど、頼る家族がいないという心配ごとをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
わたしもおふたりさま夫婦なので、妻に先立たれたり、認知症になったりした場合には、身元保証人を考えなければいけません。
高齢化社会の日本で、今後ますます単身世帯の高齢者が増えていくでしょう。
そこで、今回は失敗しない身元保証代行サービスの選び方を中心に執筆いたします。
まず、身元保証代行サービスの全貌を明らかにします。
次に身元保証代行サービスのメリット・デメリットを解説いたします。
そして、おすすめの事業者の紹介をし、事業者と利用者間に多いトラブルとその回避の仕方についてお伝えすることでしょう。
終活をするとき、一度は考える身元保証代行サービスについて一緒にみていきましょう。
興味深く、最後まで読んでいただければ幸いです。

まずはじめに、身元保証代行サービスとは何なのでしょうか。
高齢者にとって身元保証人が必要となるケースは、病院への入院時と介護施設への入所時です。
まわりに身寄りがいなければ、身元保証人を探さなければいけません。
そのような時、便利なサービスが身元保証代行サービスです。
身元保証人の役割と重要性
病院への入院時の役割としては、入院費の保証や緊急連絡先になることです。
本人に支払い能力がなければ身元保証人が保証しなければいけませんし、入院時に病状の急変があれば、病院は身元保証人に連絡します。
さらに、本人による意思決定が難しい状態であれば、治療方針の判断も求められます。
介護施設への入所時の役割としては、月額費用の保証、治療の際の手続き、緊急連絡先になるなどがあります。
亡くなったときの役割としては、遺体を引き取り、葬儀の準備やさまざまな事務手続きを行います。
介護施設に入所していた場合は、退去手続きも行う必要があるでしょう。
また、未払い料金があれば精算し、部屋の片付けや遺品の引き取り作業も行わなければいけません。
どのような人が利用するのか
・一人暮らしで、身寄りがなく、誰も頼る人がいない
・一人暮らしで家族はいるが遠方に住んでいる
・一人暮らしで家族はいるが疎遠である
・高齢の夫婦だけで子どもがいない
・家族の負担を減らしたいので事業者と契約したい
代行サービスの基本的な仕組み
契約
利用者は身元保証代行サービスを提供する事業者と契約を結びます。
サービス内容
サービス内容は身元保証人の代行ですので、その役割とほぼ同様ですが、以下に示しておきます。
①日常の生活支援
買い物の代行、通院の付き添い、配食サービスの手配など日常生活のサポートをします。また、住民票の取得や公共料金の支払いの手続き、各種申請手続きなどの代行をします。
②入院時、施設入所時
入院、入所時に必要な身元保証人、緊急連絡先となります。また、施設利用料、入院費などを一時的に立て替えたり、保証したりします。
③死後事務
死亡に関する手続き全般、関係者への連絡を行います。また、葬儀に関する事務、火葬・埋葬に関する手続きを行います。さらには、ライフラインの停止、相続人への遺品・遺産の引き渡しなど多岐にわたります。
費用
どの程度の範囲をカバーしているかなど事業者によってサービスの範囲はさまざまですので一概にはいくらとは言えませんが、100万円を超えたという人がほとんどのようです。
決して安くはありませんが、老後、死後の安心を買うという意味では価値はあるでしょう。
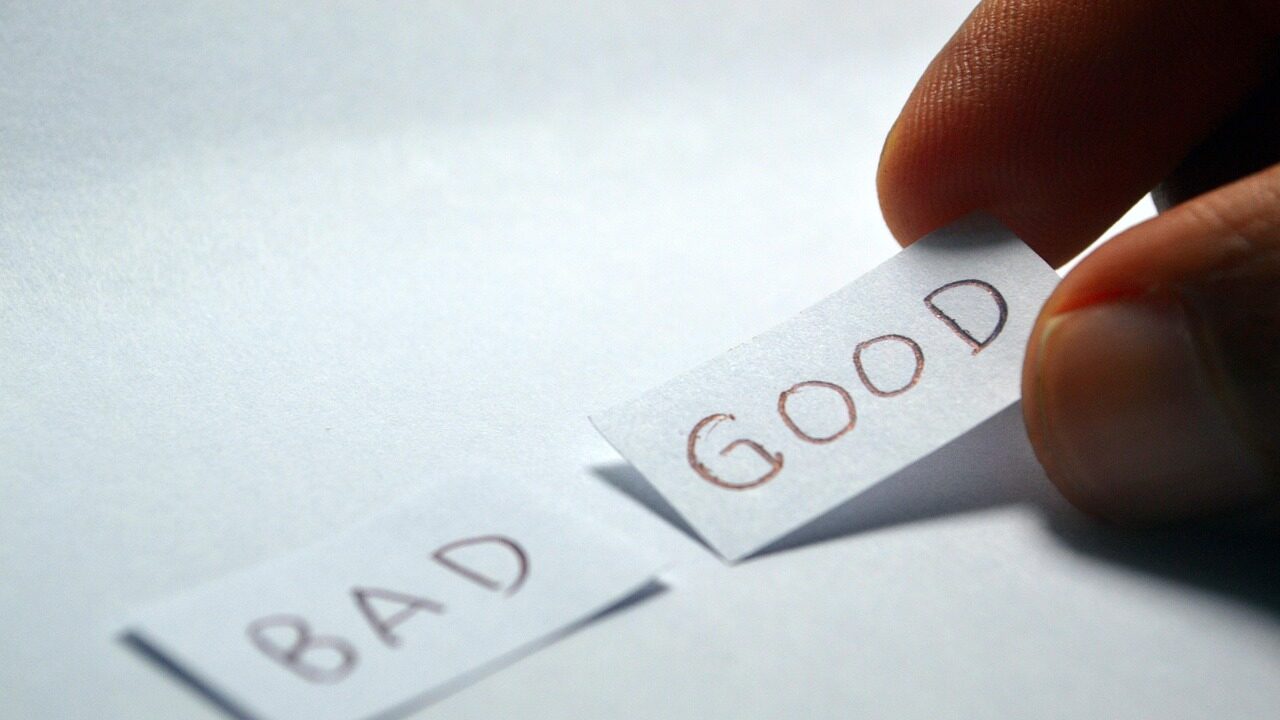
ここでは、身元保証代行サービスのメリット・デメリットを紹介いたします。
身元保証代行サービスのメリット
①人間関係に気を遣わなくて済む
身元保証代行サービスを利用すると人間関係に気を遣わなくて済みます。
なぜなら、サービスを提供する側と利用する側でマッチングしているからです。
例えば、身近な身内がいないなど、身元保証人をお願いするのに、お互い気を遣うような間柄の人しかいない場合、それぞれが負担になってしまい、関係が悪化する可能性があります。
しかしながら、身元保証代行サービスを利用すると、人間関係の悪化などの問題をクリアすることができます。
②身元保証人を探す手間がなくなる
2つ目のメリットは身元保証人を探す手間がなくなるということです。
家族や親族がいない人にとって、身元保証人を探すのはひと苦労でしょう。その労力がいらず、身元保証人を立てることができるのは大きなメリットです。
③日常生活のサポートが受けられる
3つ目のメリットは日常生活のサポートが受けられるということです。
というのも、身元保証代行サービスでは、多くの場合、日常生活のサポートがサービス内容に含まれています。
買い物や通院の付き添いなど、高齢者一人ではなかなか難しい状況の方もいらっしゃいますので、日常生活のサポートを受けられるのに魅力を感じる方もいるでしょう。
身元保証代行サービスのデメリット
①サービス提供事業者が倒産する可能性がある
1つ目のデメリットは、身元保証サービスを提供する事業者が倒産する可能性があるという点です。事業者が倒産するとサービスが利用できなくなったり、支払った費用が戻ってこなかったりする恐れがあります。
利用する会社を選ぶときは詳しい人に聞いたり、複数社を比較検討したりするとリスクを減らせるでしょう。
②費用がかかる
2つ目のデメリットは費用がかかるという点です。家族や親族に身元保証人になってもらう場合には必要ありませんが、事業者に代行サービスの提供を受けるので、利用料が発生します。
利用料の支払い方法は一括で支払うところや月額で支払うところなど事業者によってさまざまですが、身元保証だけですと30~50万円程度の費用がかかるでしょう。
③悪質な会社も存在する
3つ目のデメリットは悪質な会社も存在するという点です。高齢者という弱みにつけ込んで、高額な利用料を請求したり、契約時と契約内容が異なったりといった悪質な会社も存在します。
被害に合わないためにも、いろいろ情報を収集して、比較検討してください。
ここでは、優良な身元保証代行サービスの事業者の見つけ方や一般的な事業者の料金体系、契約時の注意点をみていきます。
信頼できる事業者の見つけ方
まず、事業者の事業内容や実績など会社概要がはっきりと公開されているかを確認しましょう。
次にサービス内容を確認します。サービス内容は事業者によってさまざまですので、安いからいい事業者であるというものでなく、高いから悪い事業者であるということでもありません。ご自身のニーズに適したサービス内容を提供している事業者が一番むだもなく、不足もなく適しているといえるでしょう。
次に料金体系ですが、こちらも事業者によってさまざまです。一括のところもあれば、月額制のところ、年会費が必要なところがあります。費用の内訳など詳細を丁寧に示してくれているところを選ぶといいでしょう。
あとは、対面で説明を受けたときの担当者の印象や口コミも選ぶポイントの1つになります。
料金体系の例
- 基本契約費用:80万円~100万円
- 身元保証費用:30万円~50万円
- 死後事務費用 (預託金):50万円~100万円
- 生活サポート費用:1時間あたり3,000円~5,000円
- 葬儀・納骨費用:275,000円~
- 死後事務手続き費用:200,000円~
契約時の注意点
契約書に細部まで明記されているか確認する
契約書に契約内容や費用に関して細かく明記されているか確認してください。その上で、記載内容が不十分であれば、業者に直接問い合わせて確認してください。
預託金の管理方法について確認する
預託金については、事業者の資産と預託金を明確に分けて管理している事業者に依頼するのが望ましいです。
遺贈寄付が前提となっていないか
身元保証代行サービスを行っている事業者の中には、報酬だけではなく遺贈寄付によって利益を出すことを目的としている場合があります。
遺贈寄付が前提となっており、実質的な負担が重い場合は再検討したほうが無難でしょう。

ここでは、おすすめの身元保証代行サービスの事業者とその運営母体の種類について解説いたします。
身元保証代行サービス会社おすすめ3選
| 特徴 | 専任担当コンシェルジュ |
| サービス | 日常生活サービス、入院時サービス、介護時サービス、緊急時サービス、連絡代行サービス、葬儀サービス、納骨サービス、行政手続きなど代行サービス、遺品整理サービス、相続サービス、公正証書作成サービス |
| 費用 | 身元保証料金:38.5万円 / 葬儀・死後事務等:148.5万円 |
| おすすめポイント | 価格設定がわかりやすい |
| 特徴 | 地域によっては引っ越し後も継続して対応可 |
| サービス | 各種同意・延命治療に関する諾否、債務保証、緊急時の連絡先、
死亡時の引き取り等 |
| 費用 | 基本料金:64.2万円 / 身元保証料金:19.8万円
葬儀・死後事務等:73万円 |
| おすすめポイント | 弁護士法人による支援あり |
| 特徴 | カスタマイズ可能な柔軟なプラン |
| サービス | 連帯保証、入院や介護の手配協力、返還金受取口座指定、身元引受等 |
| 費用 | 基本料金:47.3万円 / 身元保証料金:33万円
葬儀・死後事務等:預託金(実費) |
| おすすめポイント | 士業法人が設立 |
身元保証代行サービスの事業者に多い運営母体の種類とその特徴
一般社団法人
一般社団法人とは2人以上の社員によって設立された団体です。一般社団法人が株式会社等と違うのは、営利を目的としていないところです。そのため、「非営利法人」と呼ばれています。ただし、一般社団法人が収益の出る活動を行い、その収益を団体の運営に使うことは禁じられていません。
NPO法人
非営利団体で、地域社会への貢献を目的とする場合が多く、柔軟な対応や、地域の実情に合わせたサービスを提供してくれます。
料金設定は比較的低価格な場合もあります。
株式会社
多くは営利を目的とし、サービス内容や料金設定が比較的自由です。また、大手企業が運営するサービスも存在し、全国展開している場合もあります。
サービス内容や料金体系が明確で、オプションサービスも充実していることが多いでしょう。

ここでは、身元保証代行サービによくあるトラブルとその対処法について解説いたします。
よくあるトラブルの事例
ここでは、よくあるトラブルの事例をみていきます。
①契約内容が不明瞭である
1つ目は契約内容が不明瞭であるということです。
というのも、サービス内容は一律に決められているわけではなく、詳細の記載がない場合もあるからです。
例えば、入会金など支払いに関する手続きを先にさせられて、あとはさらっと済ませられるような契約は気をつけましょう。
②高額な費用が発生する
2つ目は高額な費用が発生するということです。
サービスを追加したことによって、高額な追加料金が発生したケースがありました。
パッケージで販売されているサービスは不要なものがあったり、急に料金があがったりしますので、注意が必要です。
③解約時に高額な手数料・違約金が請求される
3つ目は解約時に高額な手数料・違約金が請求されるということです。
契約するときは解約することはないと思っていても、状況が変わることは十分ありえます。
契約時に解約したときの返金、違約金の発生の有無もしっかり把握しておくようにしましょう。
トラブルを回避する対処法
①契約内容が不明瞭の場合、契約を交わす前に内容をよく確認し、不明な点は担当者に質問しましょう。また、契約前にご家族にも契約内容を確認してもらっておくと安心です。
ご契約時は「重要事項説明書」に沿って説明してくれるような事業者を選びましょう。
②予算を決め、その予算の範囲内で必要なサービスの契約をするようにします。また、費用の内訳を明確に提示しているか確認しておきます。
③「解約の条件」や「違約金発生の有無」「返金保証の有無」を契約前に確認しておくことが大事です。また、パッケージで購入した場合、一部解約は可能か、その時の返金はあるのかなどの疑問は契約前に解消しておきましょう。
信頼できる担当者とのコミュニケーション方法
まず、担当者が知識やスキルを十分備えており、誠実な対応をしているか見極めましょう。
また、親身になって相談に乗ってくれるかも大事なポイントです。相手の立場、利用者の立場に立って、物事を考えてくれる人でないと信頼関係は築けません。
そして、まめに連絡や相談をして、コミュニケーションを図りましょう。
契約上の関係ですが、感謝し、尊重し合える関係構築をめざしましょう。

老後に向けた準備としての利用
身寄りのないおひとりさまにとって、老後に向けて身元保証は必要となってきます。
先述した日常生活のサポートや入院時、施設入所時、また死後事務手続きなど、身元保証人がいなければ、手続きがとどこおってしまい、トラブルに発展する恐れがあります。
そうならないための備えとして、身元保証代行サービスを利用する価値はあります。
葬儀などの死後の手続きに及ぼす影響
一般的に身元保証サービスは生前に行われるサービスですが、葬儀や埋葬などは死後に行われる事柄です。
死後に行われることを生前に契約しておくものに死後事務委任契約があります。
事柄の関与が生前なのか死後なのかでサービス名が変わりますが、死後事務も一括して身元保証サービスに含まれるサービス内容となる事業者もあります。
身元保証サービスと死後事務委任契約との線引きは非常に難しく、サービスの範囲がどこまでなのかは確認しておく必要があります。
家族の負担の軽減
おひとりさまの身元保証サービスは必要ですが、家族がいても、家族の負担を減らしたいという理由で身元保証サービスを利用される方もいます。
身元保証サービスを利用することで、入院・退院などの手続きや精算、日常生活のサポートを受けられるので、家族の負担を軽減できます。
また、死後の各種手続きも数が多く、煩雑であるため、家族の負担になります。ですが、死後事務委任契約を結んでおくと、家族はわずらわしい事務手続きを回避することができ、負担をかけずに済みます。
自分の死で家族に手間をかけさせたくない気持ちが強い方は、身元保証サービスや死後事務サービスを利用するのもひとつです。

身元保証代行サービスとは、高齢者が入院や介護施設入所の際に必要となる「身元保証人」の役割を事業者が代行する仕組みのことでした。
身元保証人は入院費や施設利用料の保証、緊急時の連絡先、治療方針の判断、さらには死亡時の遺体引き取りや葬儀・遺品整理など多岐にわたる役割を担います。
しかし、身寄りがない、家族が遠方に住んでいる、または関係が疎遠で頼れない場合、保証人を確保することは難しいでしょう。そこで利用されるのが代行サービスです。
代行サービスの主な契約
①買い物や通院付き添い、公共料金の支払いなど日常生活支援
②入院・入所時の保証や緊急連絡先、費用立替
③死後事務(葬儀、埋葬、ライフライン停止、遺品整理等)
費用は事業者により異なりますが、総額で100万円を超えるケースが多いでしょう。
身元保証代行サービスを利用することのメリット
①人間関係に気を遣わず保証人を確保できる
②探す手間が省ける
③生活支援を受けられる
身元保証代行サービスを利用することのデメリット
①事業者の倒産リスク
②高額な費用
③悪質業者の存在
利用に際しては、事業内容・実績・料金体系を確認し、契約内容や預託金の管理方法を明確にしておくことが重要でしょう。
また、遺贈寄付が前提となる契約にはとくに注意する必要があります。
事業者には一般社団法人、NPO法人、株式会社などがあり、それぞれ非営利性や地域密着性、全国展開の柔軟性といった特徴を持つことを紹介しました。
おすすめの事業者として「終活協議会」「きずなの会」「全国シルバーライフ保証協会」の3つがおすすめでしょう。
トラブル事例としては契約内容の不明瞭さ、高額な追加費用、解約時の違約金などがあります。対処法としては契約前に内容を確認し、費用の内訳や解約条件を把握すること、また、信頼できる担当者と密にコミュニケーションを取ることでした。
身元保証代行サービスは終活の一環として注目されており、老後に備えた安心を確保できるだけでなく、死後の手続きまで委任できる点で有効です。
また、家族がいる場合でも、その負担軽減を目的に利用する価値があることを紹介しました。入院・施設入所・死後の煩雑な事務手続きが代行されることで、本人にとっても家族にとっても安心を得られるサービスといえるでしょう。
この記事が読者の皆さまの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
当ブログへのご連絡は、以下のフォームからご連絡ください。

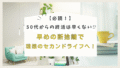
コメント